物価高が家計を圧迫し、給与明細を見ても溜息が出る。そんな毎日の中で、「消費税さえなければ…」という呟きがXやコメント欄でまるで国民の総意であるかのように聞こえてくる。
「消費税を5%に減税!」「いや、いっそ廃止だ!」。こうした主張は苦しい生活に差し込む一筋の光のよう。しかし、今日は「否」と言いたい。減税は本当に年収400万円以下の庶民の味方なのか?
なぜ今、私は消費税減税に対して反対なのか。
この記事を読むことで「消費税減税」が年収400万円以下の庶民に実は生活を苦しめてしまうことを理解することができる。日々一生懸命に働き、世の中についてしっかりと考えるあなたにこそ、ぜひ読んでもらいたい。
消費税とは何か? – 単なる「悪者」か、避けがたい「必要悪」か
消費税減税の是非を問う前に、私たちは消費税という税そのものについて理解する必要がある。税金を感情的に「悪者」と断じるのではなくその本質と構造を理解しよう。
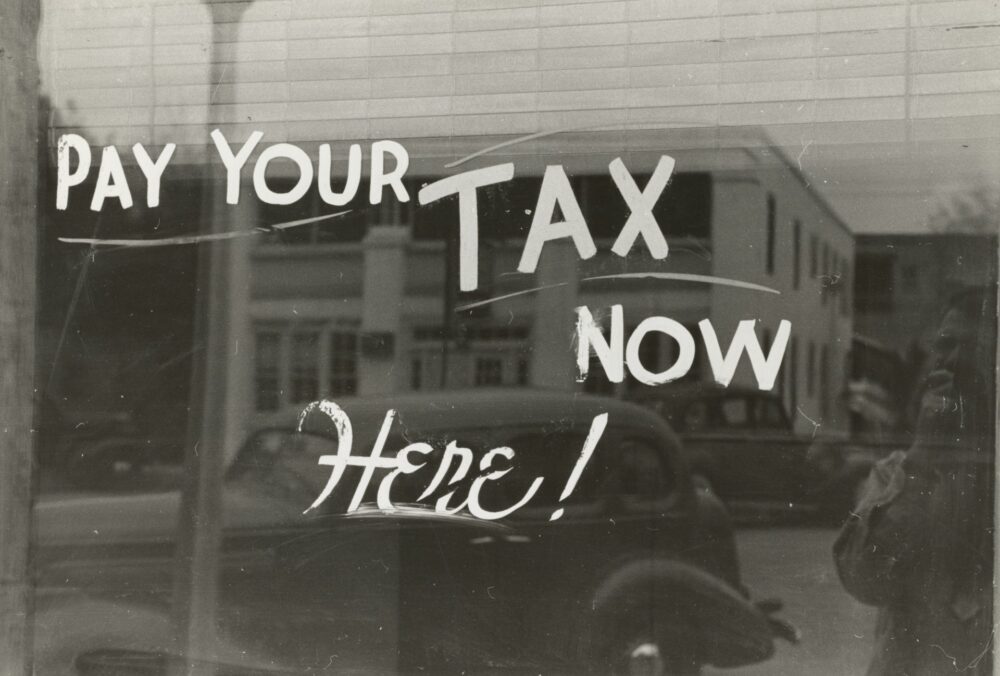
消費税に課せられた「三重の使命」
消費税は1989年の導入以来常に、議論を引き起こしてきた。しかしこの税が導入されそして引き上げられてきたのには、どうしても避けられない理由があった。
- 社会保障財源の安定化: 日本は急激な少子高齢化だ。年金、医療、介護にかかる費用は国の歳出の3分の1以上を占める。所得税や法人税だけでは支えられない。社会保障という国家の根幹を支える安定財源を確保する。これが最大の使命だ。
- 世代間の公平性: 所得税中心の税制では、負担は主に現役世代に集中する。しかし社会保障の恩恵を受けるのは高齢者を中心とした社会的弱者の方たち。消費税は消費するすべての人が負担するため、高齢者を含めた全世代で社会保障を支え合うという思想に基づいている。
- 直間比率の是正: かつて所得税や法人税が極めて高い国だった。これは勤労者や企業の負担感が高まる一方で、資産を持つ富裕層などには税が及びにくいという問題を抱えていた。消費税を導入することで税負担の歪みを是正し、より公平な税体系を目指すという狙いもあった。
つまり消費税は単に国民から広く徴収するための安易な税ではなく、日本の構造的な課題に対応するために設計された極めて重要な「仕組み」なんだ。
「逆進性」という弱点と、それを超える「所得再分配」の真実
「しかし、消費税は低所得者ほど負担が重い『逆進性』があるじゃないか!」 と主張する人がいる。まさにその通り。この指摘は正しく消費税が抱える最大の弱点だ。年収200万円の人と年収2000万円の人が同じ2000円の買い物をした時、支払う消費税額は同じでも所得に占める負担の割合は全く異なる。
この問題に対し政府は「軽減税率」の導入(食料品などを8%に据え置く)という対策を講じているが、不十分だという批判は根強い。

しかし、逆進性の負の面だけを見ていてはいけない。 我々は物事を一面だけでなく、全体像で捉える必要がある。重要なのは、「税金を払う」ことだけでなく、その税金が使われ、税金の恩恵」まで含めて考えることだ。
財務省によれば、消費税収の多くは社会保障給付(年金・医療・介護)に使われている。そしてこの社会保障給付という形での税金の恩恵は、所得が低い層ほど手厚くなる傾向がある。つまり消費税は「税金負担は逆進的だが、税金の恩恵を含めたトータルで見れば強力な所得再分配機能を持っている。全体像を見ずに「逆進性だから悪だ」と断じるのは、消費税の一部分しか見ることができていないのではないだろうか。
減税がもたらす3つのデメリット
消費税の本質を理解したところで、いよいよ「減税のデメリット」に踏み込む。仮に消費税を現行の10%から5%に減税した場合、何が起きるのか。具体的なシナリオを見ていこう。
財源の消滅
消費税率を1%引き下げるごとに、国の税収は約2.6兆円減少する。つまり5%への減税は、実に年間約13兆円もの財源が国家から消滅する。
この「13兆円」という金額がどれほど大きなものか想像できるでしょうか?
- 2024年度の防衛予算(約7.9兆円)と公共事業費(約6兆円)を足した額に匹敵する。
- 2024年度の文教及び科学振興費(約5.3兆円)の倍以上だ。
→引用:財務省https://www.mof.go.jp/zaisei/current-situation/index.html
国の根幹をなす防衛予算や公共事業費が丸々なくなってしまうくらいの規模だ。もし消費税を廃止し、この穴を埋めるにはどんな選択肢があるか?考えられるのは悲劇的な二つのシナリオがある。

実質負担の増加
最も簡単な方法は、消費税収が使われていた社会保障サービスをそのまま削減すること。我々の生活はどのように変わってしまうのか。
- 医療: 病院の窓口負担が3割から4割、5割へと引き上げられる可能性がある。高額療養費制度の上限額も大幅に引き上げられ、実質的な負担が増え「お金がなければ十分な治療が受けられない」社会となってしまう。
- 介護: 介護保険サービスの自己負担が1割から3割、4割と増加することになるだろう。社会保障費が削減されることで介護報酬が下がり特別養護老人ホームなどの数も減少、介護職の賃金減少に拍車がかかり介護サービスの質の低下が起きるだろう。そうなったとき年老いた家族をだれが見るのだろうか。
- 年金: 年金支給開始年齢のさらなる引き上げや、支給額のカットが避けられなくなる。

ここで年収400万円の世帯にをモデルに消費税の変化がどう影響するか見ていく。 消費税が5%になり極端な話、年間消費額が400万円だと仮定して減税により手取りは年間約20万円。月々1.6万円ちょっと、懐が温かくなる。
しかし減税による社会保障費削減の代償として子どもが盲腸で入院した時、窓口での支払いが10万円になったり、親の介護費用が月々3万円になったり、将来もらえるはずだった年金が大幅に減少するかもしれない。たとえ話だがどちらが年収400万円以下の庶民ににとって大きなダメージとなるかは火を見るより明らかではないか。
代替増税による弊害
「社会保障は削らず、他の税金で補填すればいい」という主張もある。しかしこれは本当だろうか。
- 法人税で補填する場合: 日本だけが大幅な法人税引き上げに踏み切れば、企業の海外流出が加速し国内の雇用は失われ、賃金も上がらなくなる。
- 国債発行(借金)で補填する場合: 物の供給に対して通貨が増えると通貨の価値が下がり物価の上昇、つまりインフレを引き起こすことになる。
- 所得税で補填する場合: 年収400万円~800万円といった中間層への大規模な増税が不可避となり、「消費税は下がったが、可処分所得はむしろ減った」という本末転倒な結果を招く。

代替財源の議論は、どの道を選んでも「詰んでいる」。
減税が招く「インフレ」というブーメラン
財源論だけで話は終わらない。消費税減税は我々の経済そのものを歪め、「インフレ」という巨大なブーメランとなって生活を直撃する。
減税によって僕たちの手取りが増え、消費意欲が高まる。一見すると良いことのように聞こえる。でも、国全体の供給能力(モノやサービスを生み出す力)が変わらない中で、みんなが一斉にお金を使い始めたらどうなるか。答えはシンプルで、モノの値段が上がる。
極端な話をしよう。今現在の手取り20万円が平均的な日本だからこそ、「100円ショップ」として成り立っている。もし減税や給付でみんなの手取りが100万円になったとしたら…?その時「100円ショップ」として存在しているだろうか。おそらく、それは「1,000円ショップ」や「1万円ショップ」になっているかもしれない。日本円の「価値」を相対的に低下させる。これと同じことが大なり小なり生じるだろう。
さらに深刻なのは、減税がもたらす富裕層への優遇。支出額が大きい富裕層ほど、減税による恩恵はケタ違いに大きくなる。彼らがその増えたお金で、株式や不動産への投資を加速させたらどうなるか?「インフレ」が生じる。結果家賃は上がり、資産を持つ者と持たざる者の格差はどんどん広がる。庶民の暮らしはますます苦しくなる。

「景気が良くなるなら、結局はみんな幸せになるんじゃないの?」 その声が聞こえてきそうだが、それにも「否」と答える。なぜなら景気回復の恩恵は決して平等には行き渡らない。
世の中には景気の波の恩恵を受けにくい人たちがいる。社会的弱者はもちろんのこと、我々の社会に不可欠な医療・福祉、そして公共サービスに従事している人々だ。医療・福祉、そして公共サービスに従事している人の給料は、国の制度(公定価格など)によって決められている部分が大きく民間の景気に連動してすぐ上がるわけではない。

しかし減税が招いた物価上昇のダメージだけは、容赦なく彼らの生活を襲う。生活苦からその職を離れていき結果、我々が受ける医療や公共サービスの質の低下という形で社会全体に跳ね返ってくる。
引用:キャノングローバル戦略研究所 https://cigs.canon/article/20220512_6770.html
では、どうすべきか? – 「再分配」
じゃあ、物価高に苦しむ私たちはただ指をくわえて耐えろというのか?いや道はあると私は信じている。私が考える真の解決策は、「消費税減税」ではない。消費税の役割である「所得の再分配」、つまりは的を絞った「給付」。

ただ、今の給付制度にも課題はあると私は感じている。残念なことに、その対象が住民税非課税世帯などに限定されがち。もちろん、その支援は絶対に必要不可欠だ。でも今の日本で本当に苦しんでいるのは住民税非課税世帯だけだろうか?
年収400万円程度の私自身もこうした給付の対象にはならない。このブログを読んでくれているあなたの中にも同じような悔しさや、もどかしさを抱えている人は少なくないのでは?
年収200万円とは言わず300万円であっても子育ての真っ最中であったり、家族の介護をしていたりと個々の事情に応じて的確な給付が必要だと考える。
給付の具体的な財源の確保は?「増税」
消費税増税の話をすると、どうしても「収入に関係なく、みんなから同じように取る税金」というイメージがつきまとう。だから、「消費税増税なんてとんでもない」と感じるのも自然なことだ。でも考えてみてほしい。所得にゆとりのある人ほど、日々の暮らしに必要なものだけでなく、より多くの、より高価なモノやサービスを消費してくれる。

娯楽や、海外旅行、あるいは高級なレストランでの食事。豊かな消費が実は社会を支えることにつながる。支払う税の「率」は同じでも、支払う税の「絶対額」は消費の大きさに比例して多くなる。集められた貴重な財源は今の社会で最も支援を必要としている人々のもとにいく。
予期せぬ病や介護に直面し、明日の光を見失いかけている人々の心を照らす温かい灯火になるかもしれない。
再分配がみんなで底上げしていくことになる。
まとめ
消費税減税は、一見すると私たちの生活を楽にしてくれる魔法のように見える。しかし代償は私たちが築き上げてきた社会保障というセーフティネットの崩壊、安心して暮らせる社会とは真逆の方向に進む。特にその日の暮らしを懸命に支える年収400万円以下の層にとって、そのリスクはメリットを遥かに凌駕すると思われる。
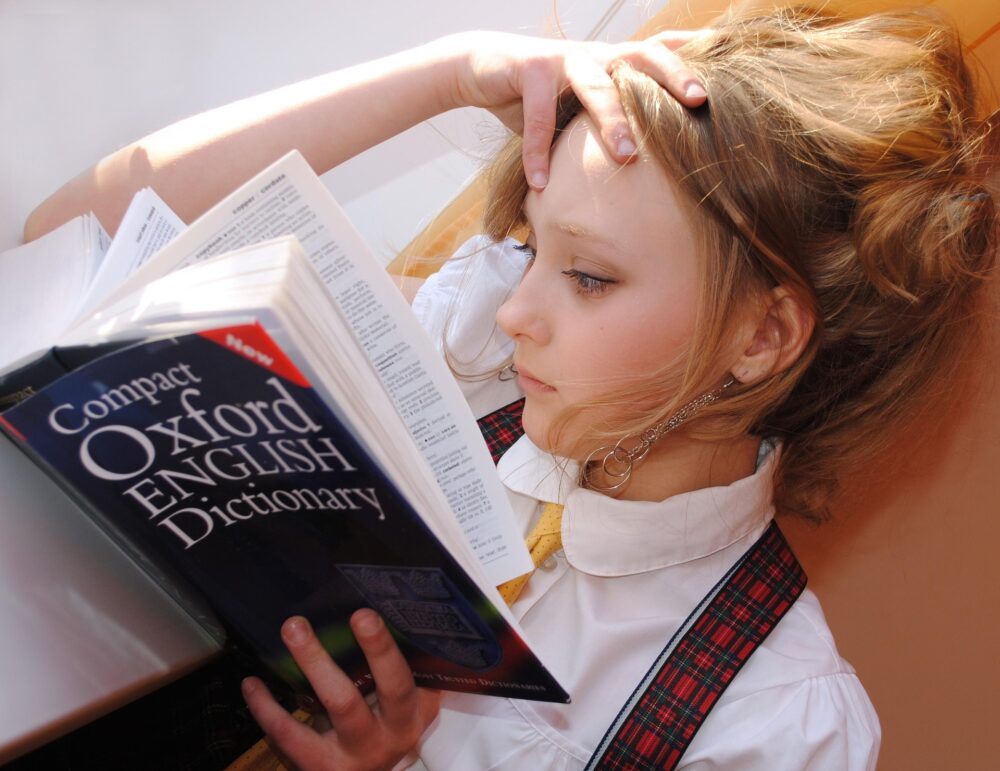
ネットでは聞こえのいい言葉がたくさん出回っている。そんな言葉に惑わされないように私たちはどうすればいいのか。
日本国民として、以下の三つの視点を持ち続けることが不可欠だと私は考える。
- 時間軸で思考する: 今この瞬間の損得だけでなく、5年後、10年後の長期的な社会の影響を想像する。
- 恩恵と負担を常にセットで問う: 「消費税減税」という言葉を聞いたら、反射的に「では、どのサービスが削られ、誰が新たなる負担を負うのか?」と考える。
- 言葉の裏にある「世界観」を読む: 政治家が何かを主張する時、その言葉の裏にある「どんな社会を目指しているのか」という考えを自分なりに考える。
私たち年収400万円以下の人が個人でできること
現在の原材料高騰によるインフレによって、我々の生活はじわじわと苦しくなっていく。
では我々はこのインフレという大きな波に、ただ飲み込まれるしかないんだろうか?
そんなことはない。国も実は「自分の身は自分で守れ」というメッセージをある制度に込めて発している。
それがNISA。インフレで現金の価値が下がるならその一部を成長する資産に換えておく。
そのための強力な武器として、国はNISAという非課税制度を用意してくれた。

つまり「消費税減税」のような甘い言葉に惑わされず、社会が直面しているインフレのリスクを直視すること。そしてそのリスクから自分の生活を守るための具体的な自己防衛策として、NISAのような制度を賢く活用すること。
世の中を広く見るが、これからの時代を生き抜く上でものすごく重要になってくる。
今回は消費税減税というテーマについて、私なりの視点を語らせて頂きました。もちろん、これが唯一の正解だと言うつもりはありません。
あなたはこの問題、どう考えますか?
「それでも減税すべきだ」「こういう視点が抜けている」どんな意見でも構いません。ぜひ、コメント欄であなたの考えを聞かせてください。議論を深めることがより良い社会への第一歩だと信じています。そしてもしこの記事が少しでもあなたの思考の助けになったなら、SNSでシェアしていただけるとこれ以上嬉しいことはありません。
